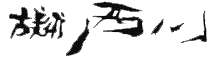骨董品の魅力は多種多様ですが、その中でもひときわ鮮やかな色彩と大胆なデザインで人々を惹きつけるのが「九谷焼(くたにやき)」です。石川県南部(加賀市、小松市、能美市など)で作られる色絵磁器の総称で、その歴史は古く、多くの骨董品愛好家を魅了し続けています。今回は、日本の代表的な磁器である九谷焼について、その歴史から様々な様式、形や種類(用途)まで、初心者に分かりやすく解説します。磁器の王道ともいえる伊万里焼とはまた異なる、加賀文化が生んだ華麗な九谷焼の世界を探訪しましょう。
九谷焼の歴史 – 幻の古九谷から百花繚乱の再興、そして現代へ
九谷焼の歴史は、大きく二つの時代に分けられます。
- 古九谷 (こくたに): 江戸時代前期の明暦年間(1655年頃)、加賀藩の支藩である大聖寺藩が、領内の九谷村(現在の加賀市山中温泉九谷町)で磁器の生産を始めたのが起源とされています。加賀百万石の豊かな財力を背景に、狩野派の名匠・久隅守景(くすみもりかげ)の指導もあったと伝えられ、緑・黄・紫・紺青・赤の「九谷五彩」を用いた、豪放で力強く、絵画的な作風が特徴です。しかし、この古九谷はわずか50年ほどで突然廃窯してしまいます。その理由は諸説あり、未だ謎に包まれています。生産期間が短かったため、現存する古九谷は極めて少なく、骨董品としての価値は非常に高いものとなっています。
- 再興九谷: 古九谷が途絶えてから約100年後の江戸時代後期、文政年間(1807年頃)に加賀藩の奨励によって九谷焼は再興の時代を迎えます。京都から名工・青木木米(あおきもくべい)を招いて開かれた春日山窯を皮切りに、若杉窯、吉田屋窯、宮本屋窯(飯田屋八郎右衛門)、永楽窯など、多くの窯が次々と興り、それぞれが特色ある作風を生み出しました。
- 春日山窯: 青木木米が指導し、中国風の赤絵や染付などを作りました(木米風)。
- 若杉窯: 藩の殖産興業として始められました。
- 吉田屋窯: 古九谷の「青手」(緑・黄・紫・紺青が主体の様式)の再興を目指し、器全体を塗り埋めるような濃厚な色彩が特徴です。
- 飯田屋窯(宮本屋窯): 「赤絵細描(あかえさいびょう)」と呼ばれる、極めて細かい赤い線で人物などを描き込む様式で知られます(八郎手)。
- 永楽窯: 京焼の名工・永楽和全(えいらくわぜん)が招かれ、赤地に金彩を施した豪華な「金襴手(きんらんで)」様式を完成させました。 この再興九谷の時代の作品は、多様な様式が花開き、骨董品市場でも数多く見ることができます。
- 明治以降: 明治時代に入ると、九谷庄三(くたにしょうざ)が、西洋の顔料なども取り入れながら、これまでの様々な様式を集大成した「彩色金襴手」を確立。その華やかな作風は「ジャパンクタニ」として海外でも高く評価され、輸出産業として発展しました。この頃から、素地作り、絵付けなど、工程ごとの分業化も進みました。
- 現代: 現代の九谷焼は、伝統的な技法や様式を受け継ぎながらも、作家たちが自由な発想で新しい表現を追求し、多様な作品が生み出されています。
九谷焼の多彩な様式(特徴)
九谷焼の最大の魅力は、その鮮やかで美しい「上絵付け(うわえつけ)」です。基本となるのは「九谷五彩」と呼ばれる緑、黄、紫、紺青、赤の和絵具ですが、時代や窯、様式によってその表現は様々です。骨董品の九谷焼を見分ける上でも、様式を知ることは重要です。
- 古九谷様式: 五彩を大胆に使い、力強い線と構図で描かれたもの。余白を生かした絵画的な表現が特徴です。「青手古九谷」と呼ばれる、緑、黄、紫、紺青を主とした濃厚な色彩のものもあります。
- 木米様式 (春日山窯): 全体を赤で塗り、人物などを中国風に描いた赤絵が代表的。
- 吉田屋様式 (吉田屋窯): 青手古九谷を再興。緑、黄、紫、紺青の四彩を用い、文様で器全体を塗り埋めるような重厚な彩色が特徴。赤を使わないのが原則です。
- 飯田屋様式(八郎手) (宮本屋窯): 赤絵細描。非常に細かい赤い線で、主に人物や風景、唐子(からこ)などを緻密に描き込みます。金彩で縁取ることもあります。
- 永楽様式 (永楽窯): 赤で下塗りした上に、金彩で華やかな文様を描く「金襴手」。永楽和全が得意とした技法です。
- 庄三様式 (九谷庄三): 古九谷から再興九谷までの様々な様式(赤絵、金襴手、青手など)と、西洋から輸入された顔料などを融合させた、豪華絢爛な様式。「彩色金襴手」とも呼ばれます。
これらの様式は、時代や作り手の個性を反映しており、骨董品の九谷焼の多様性を生み出しています。
九谷焼の形と種類(用途)
加賀百万石の華やかな文化の中で育まれた九谷焼は、様々な形や用途の器が作られてきました。
- 食器類:
- 皿: 食卓の中心となる大皿から、取り皿として便利な中皿・小皿、形も丸皿、角皿、変形皿など多種多様です。特に骨董品の大皿には、その時代の粋を集めた豪華な絵付けが見られます。
- 鉢: 深さのある器で、煮物やサラダなど、様々な料理に使われます。
- 碗: 飯碗や湯呑、蕎麦猪口など、日常的に使う器も九谷焼で作られています。
- 酒器: 徳利(とっくり)や盃(さかずき)や盃洗は、晩酌や宴席を華やかに彩ります。
- 茶器: 急須や湯冷ましや茶碗など。
- 置物・装飾品:
- 獅子、狛犬: 魔除けや縁起物として飾られます。
- 招き猫、七福神: 商売繁盛や福を招く縁起物として人気があります。
- 人物像: 美人画や子供を描いたものなど。
- 花瓶: 花を生けるだけでなく、それ自体が空間を彩る装飾品となります。
- 茶道具:
- 茶碗、水指(みずさし)、蓋置(ふたおき)など、茶道で用いられる道具も作られています。
これらの器は、実用品としてだけでなく、美術品としての価値も高く評価されています。骨董品として集める際は、こうした種類の多様性も楽しみの一つです。
伊万里焼と九谷焼 – 日本磁器の二つの潮流
日本の磁器といえば、伊万里焼(有田焼など)が広く知られています。江戸時代初期に始まった伊万里焼は、染付から色絵まで多様な製品を生み出し、国内だけでなく海外へも大量に輸出され、日本の磁器生産をリードしてきました。
一方、九谷焼は、伊万里焼とは異なる歴史と文化背景を持つ磁器です。加賀藩という独自の文化圏で生まれ、特に色絵において伊万里焼とは違った大胆さや重厚さ、華やかさを追求しました。伊万里焼が比較的薄手で軽やかな作風が多いのに対し、九谷焼(特に古九谷や吉田屋様式)には厚手で重厚な作りのものが見られます。
伊万里焼も九谷焼も、日本の磁器を代表する存在であり、骨董品の世界ではどちらも多くの愛好家がいます。それぞれの産地の歴史や特色を知ることで、骨董品選びの視点が広がり、より深くその魅力を理解することができるでしょう。

骨董品としての九谷焼を選ぶ楽しみ

華やかな九谷焼の骨董品に興味を持ったら、どこに注目して選べばよいでしょうか?
- 初心者の方へ: まずは「状態」を確認しましょう。割れや欠け、ヒビ(ニュウ)がないか、絵の具の剥落はないか、修復の跡などをよく見ます。次に、気に入った「色合い」や「デザイン(様式)」で選ぶのがおすすめです。裏側にある「銘(窯印や作者名)」も確認してみましょう。
- 少し慣れてきたら: どの「時代」の、どの「様式」なのかを見極めてみましょう。同じ様式でも、時代や作り手によって微妙な違いがあります。
- 古九谷」の見極めや、再興九谷の各窯(吉田屋、飯田屋など)の名品、あるいは明治期の九谷庄三などの有名作家から現代の九谷焼作家の作品も探すのも骨董品収集の醍醐味です。
九谷焼の骨董品は人気が高いため、残念ながら模倣品や後年の写しなども存在します。信頼できる骨董品店やネットショップを選び、納得のいく説明を受けてから購入することが大切です。
まとめ:日常に加賀の華を – 九谷焼の世界
九谷焼は、その大胆な構図、鮮やかな色彩、そして多様な様式で、私たちを魅了する日本の代表的な色絵磁器です。幻と言われた古九谷から、百花繚乱の再興九谷、そして世界を魅了したジャパンクタニまで、その歴史は加賀百万石の文化と共に歩んできました。
骨董品の九谷焼を手にすることは、単に古い器に触れるだけでなく、その時代の空気、職人の情熱、そして日本の美意識に触れることでもあります。伊万里焼など他の産地の骨董品と見比べてみるのも面白いでしょう。
ぜひ、あなたも色鮮やかな九谷焼の世界に足を踏み入れてみませんか? 日常の食卓や空間に、加賀の華やかさをもたらしてくれる一品がきっと見つかるはずです。