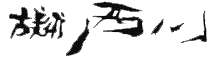日本の伝統的な建具でありながら、壮大な絵画空間をも創り出す「屏風(びょうぶ)」。骨董品としての屏風は、その場を仕切り、風を防ぐという実用性だけでなく、描かれた絵画を通して歴史や文化、そして高い芸術性を私たちに伝えてくれます。今回は、知っているようで意外と知らない屏風の世界について、その歴史から大きさ、種類(用途)まで、骨董品初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
屏風とは?骨董品としての魅力
屏風とは、数枚のパネル(「扇(せん)」または「曲(きょく)」と数えます)を蝶番(ちょうつがい)で繋ぎ合わせ、折りたためるようにしたものです。主な役割は、部屋の間仕切りや風よけですが、同時にその表面には美しい絵画や書が施され、空間を飾る調度品としても重要な役割を果たしてきました。
骨董品としての屏風の魅力は、この実用性と芸術性の融合にあります。当時の権力者や富裕層が、一流の絵師に描かせた豪華絢爛な屏風から、日常の中で使われたであろう素朴な屏風まで、多種多様です。一枚の屏風から、それが作られた時代の空気感や、人々の暮らし、美意識を感じ取ることができるのは、骨董品ならではの醍醐味と言えるでしょう。

屏風の歴史:時代と共に変化した姿
屏風の歴史は古く、そのルーツは古代中国にまで遡ります。日本には奈良時代頃に伝来したとされています。

- 古代~平安・鎌倉時代:
- 当初は宮中や貴族の邸宅で、主に儀礼的な場面や風よけとして用いられました。
- 平安時代には、大和絵(やまとえ)の主題として屏風絵が描かれるようになり、『源氏物語』などにもその様子が見られます。
- 室町~安土桃山時代:
- 武家社会が発展するとともに、屏風も権力の象徴として豪華なものが作られるようになります。
- 特にこの時代は、城郭建築の内部を飾る「金碧障壁画(きんぺきしょうへきが)」が隆盛し、金箔地に鮮やかな色彩で勇壮なモチーフ(龍虎、花鳥、合戦図など)が描かれた屏風が多く制作されました。狩野派などの絵師が活躍した時代です。骨董品としても非常に価値の高い屏風がこの時代に生まれています。
- 江戸時代:
- 社会が安定し、町人文化が花開くと、屏風の需要も多様化します。
- 大名や公家だけでなく、裕福な商人たちも屏風を求め、狩野派、土佐派、琳派、円山四条派、浮世絵師など、様々な流派の絵師が屏風絵を手がけました。より装飾的で、個性的、あるいは庶民的な題材の屏風も登場します。骨董品市場で見かける屏風の多くはこの時代のものです。
- 明治以降:
- 生活様式の西洋化に伴い、日常的な道具としての屏風の需要は減少していきます。
- しかし、日本画の重要な形式として、また美術工芸品として制作は続けられました。古い時代の屏風は「骨董品」として収集・保存の対象となり、その価値が再認識されるようになります。
屏風の大きさと種類(用途):多様な姿とその役割
屏風は、その大きさや形状、そして用途によって様々な種類があります。骨董品を選ぶ際にも、これらの知識は役立ちます。
- 大きさの単位「扇(せん)」または「曲(きょく)」:
- 屏風のパネル一枚を「扇」または「曲」と呼びます。パネルが2枚なら「二曲屏風」、6枚なら「六曲屏風」となります。一般的には、六曲一双(ろっきょくいっそう:6枚パネルの屏風が左右一対)が最も格式が高いとされます。
- 高さ: 「本間(ほんけん)」サイズ(約170~180cm)と、それより少し低い「京間(きょうま)」サイズ(約150~170cm)が標準的ですが、これより大きいもの、小さいものもあります。
- 小型の屏風:
- 枕屏風(まくらびょうぶ): 寝床の枕元に立てる小型(高さ50cm程度)の二曲屏風。風よけや目隠しに使われました。
- 風炉先屏風(ふろさきびょうぶ): 茶室で、風炉(茶釜をかける炉)の前に立てる低い二曲屏風。道具を引き立て、空間を区切る役割があります。骨董品としても人気があります。
- 種類(用途):
- 間仕切り・風よけ: 屏風本来の機能です。広い空間を区切ったり、風や視線を遮ったりするために使われました。
- 儀式・設え(しつらえ):
- 祝儀(お祝い事): 結婚式(金屏風の前で記念撮影をするのはその名残)や節句飾りなどで、場を華やかに演出するために用いられました。吉祥文様(松竹梅、鶴亀など)が描かれたものが好まれます。
- 不祝儀(弔事): 葬儀の際に、故人の枕元に立てる「枕屏風」には、白地に山水画などが描かれることがありました(逆さ屏風の風習)。
- 茶の湯: 前述の風炉先屏風のほか、客座と点前座を区切るために大きな屏風が使われることもありました。
- 装飾・鑑賞: 屏風に描かれた絵画そのものを美術品として鑑賞し、室内を飾る目的で使われます。四季の草花、名所図、物語絵、山水画など、描かれるテーマは多岐にわたります。骨董品の屏風は、まさに「移動できる壁画」と言えるでしょう。
骨董品としての屏風選びのヒント

骨董品の屏風は、状態や描かれた内容によって価値が大きく異なります。選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。
- サイズ:屏風のサイズは大きいものが多いので、まず自分の飾りたい場所のサイズを測りそれに合ったサイズの物を探す。
- 画題・様式: どのような絵が、どの流派の様式で描かれているかを確認します。自分の好みや飾りたい空間に合うかどうかが重要です。
- 落款(らっかん)・印章: 作者を示すサインや印があるか確認します。有名な絵師のものであれば価値は高まりますが、無名の作品にも素晴らしいものは多くあります。
- 保存状態:
- 絵画部分: 絵の具の剥落、シミ、汚れ、破れなどがないか。
- 本紙・絹: 経年による劣化、虫食い、折れ、破れなど。
- 蝶番: スムーズに開閉できるか、傷みがないか。
- 縁(ふち): 歪みや破損がないか。
- 修復: 骨董品は何らかの修復が施されていることが多いです。修復が丁寧に行われているかどうかも確認しましょう。
まとめ:屏風と骨董品の奥深い世界へ
屏風は、単なる間仕切りや風よけではなく、日本の美意識と歴史が凝縮された芸術的な骨董品です。その壮大なスケール、描かれた絵画の美しさ、そして空間を演出する力は、現代の私たちの暮らしにも新たな彩りを与えてくれます。
当ネットショップでは、様々な時代、様式の屏風の骨董品を取り扱っております。お部屋のアクセントとして、またコレクションとして、あなただけの特別な屏風を見つけてみませんか? 屏風が持つ独特の魅力と、骨董品の奥深い世界に触れる一助となれば幸いです。