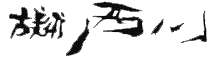「骨董品」と聞くと、少し敷居が高いイメージがあるかもしれません。しかし、その中でも「伊万里焼」は、日本の食卓や生活空間を彩ってきた身近な存在であり、骨董品の世界への入り口としても大変人気があります。今回は、多くの人々を魅了し続ける伊万里焼の歴史と、その多様な形や種類(用途)について、骨董品初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
伊万里焼とは?骨董品としての魅力

伊万里焼(いまりやき)とは、現在の佐賀県有田町周辺で江戸時代初期から焼かれた磁器の総称です。なぜ有田で焼かれたのに「伊万里焼」と呼ばれるのでしょうか? それは、製品が近くの伊万里港から積み出され、国内外へ流通したことに由来します。「有田焼」も同じ産地の焼き物を指しますが、特に江戸時代に作られ、伊万里港から出荷された古い時代のものを指して「伊万里焼」と呼ぶことが骨董の世界では一般的です。
伊万里焼の魅力は、何と言ってもその美しさと多様性にあります。透き通るような白い磁肌に描かれた鮮やかな絵付けは、時代や様式によって様々な表情を見せてくれます。丈夫で実用的な器が多いことも、骨董品としてだけでなく、日々の暮らしで楽しむことができる理由の一つです。
伊万里焼の歴史:時代を彩った美の変遷
伊万里焼の歴史は約400年。その長い歴史の中で、技術やデザインは大きく変化し、様々な様式が生まれました。
骨董品としての価値を知る上でも、その歴史を辿ることは非常に重要です。

- 江戸時代初期(17世紀前半):初期伊万里 1610-1630年代
- 日本で初めて磁器が焼かれたのがこの時代です。朝鮮の陶工・李参平らによって技術が伝えられました。
- 初期の伊万里焼は「初期伊万里」と呼ばれ、素朴で力強い作風が特徴です。染付(藍色)で簡単な文様が描かれたものが多く、まだ磁器としての洗練度は高くありませんが、骨董品としてはその希少性と味わい深さから高い人気があります。
- 江戸時代前期・中期(17世紀中盤~18世紀):様式の確立と黄金期
- 技術が向上し、様々な様式が花開いた伊万里焼の黄金期です。
- 古九谷様式(こくたにようしき)1640-1670年代
- 染付の他にも赤、緑、黄、紫、紺などの濃い釉薬を使い、大胆な構図で力強く描かれた様式。骨董市場でも特に人気の高い様式の一つです。
- 柿右衛門様式(かきえもんようしき)1670-1700年代
- 乳白色の濁手(にごしで)と呼ばれる素地に、赤を主調とした繊細で優美な絵付けが特徴。余白を生かした構図は、ヨーロッパの王侯貴族にも愛されました。柿右衛門様式の骨董品は、その上品さから現代でも根強い人気があります。
- 金襴手(きんらんで)1700-1720年代
- 染付や赤絵の上に、さらに金彩を施した豪華絢爛な様式。国内外で非常に人気を博し、伊万里焼の代表的なイメージとなりました。祝宴の席などで使われることが多く、骨董品としても華やかさが際立ちます。


- 江戸時代中期~明治時代 古伊万里 1720-1900年頃
- 技術はさらに爛熟し、より精緻で多様な製品が作られるようになります。国内向けの日常食器の生産が盛んになる一方で、ヨーロッパへの輸出も続けられました。
- 明治時代に入ると、産業化の波の中で大量生産も行われるようになりますが、職人の手による良質な伊万里焼も作られ続けました。この時代の骨董品は、比較的入手しやすいものも多く、気軽に楽しめる魅力があります。
伊万里焼の形と種類(用途):暮らしを彩った器たち
伊万里焼は、その長い歴史の中で、人々の暮らしに合わせて様々な形の器が作られてきました。骨董品として伊万里焼を見る際、どのような用途で作られたのかを知ると、より深くその魅力を理解できます。
- 皿: 食卓の中心となる器。丸皿、角皿、変形皿など形は様々。大きさも豆皿から尺皿(直径約30cm)を超える大皿まで多岐にわたります。文様も、吉祥文、花鳥風月、山水、人物、幾何学文様など、時代や様式によって実に豊かです。骨董品としてもコレクションしやすいアイテムです。
- 鉢: 深さのある器で、煮物や和え物などを盛るのに使われました。大鉢、中鉢、小鉢があり、形状も様々です。見込み(内側)の文様も美しく、食卓を豊かに彩ります。
- 碗: ご飯茶碗や汁碗など、日常的に使われる器。手に持って使うため、持ちやすさや口当たりの良さも考慮されています。骨董品の碗は、手に取ると作り手の温もりを感じられるようです。
- 猪口(ちょこ): 元々は蕎麦つゆや湯呑み、酒器として使われた小さな器。「そば猪口」が有名ですが、向付(むこうづけ:懐石料理で刺身などを盛る器)としても使われました。コレクターが多く、様々な文様を集める楽しみがあります。骨董品の中でも特に人気の高いジャンルです。


- 徳利(とっくり): 酒を入れる器。時代によって形状が変化し、瓢箪型、角型、ラッパ型などがあります。絵付けも様々で、酒席を楽しく演出します。
- 茶道具: 茶碗、水指、建水など、茶の湯で使われる道具も作られました。特に輸出用ではなく、国内の数寄者向けに作られたものは、侘び寂びの精神を反映した逸品も存在します。
- 花器: 花を生けるための壺や瓶。空間を華やかに彩る装飾品としての役割も担いました。大型のものは、骨董品として存在感があります。
- その他: 火入れ(タバコ用)、香炉、硯、置物など、生活に関わる様々なものが伊万里焼で作られました。
骨董品としての伊万里焼選びのヒント(初心者向け)
骨董品としての伊万里焼に興味を持ったら、まずは気軽に手に取ってみるのが一番です。

- 高台(こうだい)を見る: 器の底の部分を「高台」といいます。高台の作りや土の色、釉薬のかかり具合、窯印は、年代や窯元を見分けるヒントになります。
- 絵付けの様式: 上記で紹介したような様式の特徴を知っておくと、おおよその時代を推測できます。
- 傷や状態: 骨董品には経年による傷や欠け(ホツ)、ニュウ(ひび)があることも多いです。それもまた味わいですが、状態は価格にも影響します。
- まずは好きなものから: 難しく考えず、自分の感性に響くデザインや形の伊万里焼から選んでみるのがおすすめです。
まとめ:伊万里焼と骨董品の奥深い世界へ
伊万里焼は、日本の美意識と職人の技が結晶した、世界に誇る磁器です。その歴史を知り、様々な形や用途に思いを馳せることで、骨董品としての魅力はさらに深まります。
当ネットショップでは、初期伊万里から明治時代のものまで、様々な伊万里焼の骨董品を取り揃えております。ぜひ、あなただけのお気に入りの一点を見つけて、日々の暮らしに取り入れてみませんか?
伊万里焼の世界、そして骨董品の奥深い魅力に触れるきっかけとなれば幸いです。