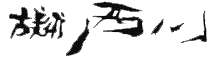骨董品の世界には、驚くほど精巧で、遊び心にあふれた小さな宝物が存在します。それが「根付(ねつけ)」「印籠(いんろう)」「緒締(おじめ)」です。これらは主に江戸時代、帯に様々な物を提げて持ち歩く「提げ物(さげもの)」として、実用性と装飾性を兼ね備えたアイテムとして発展しました。今回は、骨董品としても国内外で高い人気を誇る根付・印籠・緒締について、その歴史や役割、素材、技法、そして日本の生活の中でどのように使われてきたのかを、初心者の方にも分かりやすく解説します。伊万里焼など他の骨董品とはまた違う、ミクロな芸術の世界を覗いてみましょう。
三位一体の提げ物 – 印籠・根付・緒締の関係
まず、この三つの関係性を理解しましょう。
- 印籠 (Inro): 主に薬などを入れる携帯用の小さな容器。複数の段が重なった構造。
- 根付 (Netsuke): 印籠などを帯から提げる際に、紐の端につけて帯に引っ掛け、滑り止め(留め具)の役割をするもの。
- 緒締 (Ojime): 印籠の蓋が開かないように、また根付の位置を調整するために、印籠と根付を繋ぐ紐に通してスライドさせる小さな玉(ビーズ状のもの)。
これらは一本の紐で繋がり、セットで使われるのが基本でした。着物にポケットがなかった時代、人々はこの提げ物を使って必要なものを携帯していたのです。

印籠 (いんろう) – 精緻な技巧が光る携帯ケース
歴史と用途: 印籠の起源は古く、当初は名前の通り印鑑や朱肉を入れるためのものでした。しかし、江戸時代に入ると、薬を携帯するための容器として広く普及しました。武士や裕福な町人たちは、実用的な薬入れとしてだけでなく、自身の身分や財力、そして趣味の良さを示すための装飾品として、凝った意匠の印籠を競って持つようになりました。骨董品として現存する印籠には、当時の粋や美意識が凝縮されています。
構造: 通常、3段から5段程度の小さな箱がぴったりと重なり合い、側面を貫通する紐で一つにまとめられています。各段が精密に作られているため気密性が高く、薬の品質を保つのに適していました。
素材と技法: 最も一般的なのは漆器で、特に蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)といった高度な漆芸技法が惜しみなく用いられました。金銀をふんだんに使った豪華なものから、侘びた風情のものまで様々です。その他、木彫、象牙、金属、稀には陶磁器(例えば、伊万里焼のような磁器で作られた印籠も存在した可能性はありますが、極めて珍しいでしょう)なども見られますが、漆器が主流です。その小さな面に施された精緻な蒔絵は、まさに日本の漆工芸の真骨頂と言えるでしょう。
根付 (ねつけ) – 小さな彫刻に込められた魂
歴史と役割: 根付は、印籠や煙草入れ、巾着(きんちゃく)などを帯から提げる際の「留め具」として生まれました。紐の端につけ、帯の上から差し込むことで、提げ物がずり落ちるのを防ぎます。当初は単純な形の木片や貝殻なども使われましたが、江戸時代中期以降、平和な世の中が続き、町人文化が花開くと、根付は単なる実用品から、高度な彫刻技術が注ぎ込まれた芸術品へと昇華していきます。様々な題材が、驚くほど生き生きと、そして時にユーモラスに表現されました。骨董品としての根付は、その芸術性の高さから海外のコレクターにも非常に人気があります。

素材: 根付の素材は非常に多彩です。
- 動物素材: 象牙、ウニコール(一角鯨の牙)、鹿角、鯨歯、猪牙、水牛角など
- 木材: 黄楊(つげ)、黒檀(こくたん)、一位(いちい)、桜、柿など
- その他: 金属(金、銀、銅、鉄など)、陶磁器(伊万里焼などの窯で作られた根付も存在します)、ガラス、珊瑚、瑪瑙(めのう)、琥珀(こはく)、竹、胡桃など
形状・種類: 根付には様々な形状があります。
- 形彫根付(かたぼりねつけ): 人物、動物、神仏、妖怪、物語の一場面、静物などを立体的に彫り出したもの。最も種類が豊富で、根付の代表的な形式です。
- 饅頭根付(まんじゅうねつけ): 文字通り、平たい円盤状(饅頭形)の根付。表面に彫刻や象嵌、蒔絵などが施されます。
- 鏡蓋根付(かがみぶたねつけ): 饅頭根付の一種で、本体(主に象牙や木)に窪みをつけ、そこに彫金などを施した金属製の円盤(蓋)をはめ込んだもの。
- 差根付(さしねつけ): 帯と体の間に差し込んで使う、細長い形状の根付。煙管(きせる)や矢立(やたて)を模したものなどがあります。
- 面根付(めんねつけ): 能面、狂言面、伎楽面、神楽面などを小さく彫り出したもの。表情豊かで人気があります。
これらの根付は、骨董品として一つ一つが異なる表情を持ち、コレクションの楽しみが尽きません。
緒締 (おじめ) – 小さなアクセントの機能美
役割: 緒締は、印籠と根付を繋ぐ紐の中間に位置し、上下にスライドさせて印籠の蓋が不用意に開くのを防いだり、根付の位置を固定したりする役割を果たします。直径1〜2cm程度の小さな玉ですが、提げ物全体のアクセントとして重要な存在でした。
素材と形状: 素材は根付と同様に非常に多様で、象牙、木、金属、珊瑚、ガラス、伊万里焼などの陶磁器、瑪瑙や翡翠(ひすい)といった貴石なども使われました。形も単なる球形だけでなく、動植物や器物を小さく彫刻したもの、透かし彫りや象嵌などの細工が施されたものなど、小さいながらも技巧が凝らされています。骨董品の提げ物セットでは、印籠や根付と素材や意匠(デザイン)を合わせて作られていることも多く、その統一感も魅力の一つです。
生活の中での使われ方 – 江戸の粋なファッションアイテム

印籠、根付、緒締は、紐で一つに繋がれ、男性が帯の間に根付を挟み、印籠などを体の脇に提げて携帯しました。これは単に物を持ち運ぶための道具ではなく、持ち主の身分、財力、そして何よりも「粋」や「洒落」といった美意識を表現するための重要なファッションアイテムでした。
武士は公の場では格式に合わせた提げ物を、町人は財力に応じて凝った意匠のものを身につけました。歌舞伎役者や力士、文化人なども、個性的な提げ物を愛用したと言われています。骨董品として残る提げ物からは、当時の人々の生活様式や流行、美意識を垣間見ることができます。
伊万里焼と提げ物の接点
提げ物の主な素材は漆器(印籠)や木彫・象牙(根付)ですが、日本の多様な工芸技術がこの小さな世界にも反映されています。例えば、根付や緒締の素材として、伊万里焼をはじめとする陶磁器が用いられることもありました。磁器製の根付や緒締は、木や象牙とは異なる硬質な質感、染付や色絵による独特の色彩を持ち、骨董品の中でもユニークな存在です。数は多くありませんが、伊万里焼の窯などで作られた可能性も考えられ、当時の工芸の広がりを示唆しています。このように、主流ではない素材の骨董品を探してみるのも面白いかもしれません。
骨董品としての根付・印籠・緒締を選ぶポイント
これらの小さな骨董品を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。
- 初心者の方へ: まずは印籠・根付・緒締が「セットで揃っているか」を確認しましょう(もちろん単体でも買えることもあります)。次に「状態」です。印籠の漆の剥げや割れ、根付の欠けや摩耗、緒締の傷、紐の状態などをよく見ます。「彫刻や蒔絵の精緻さ」や「デザインの面白さ」で選ぶのも良いでしょう。
- 少し慣れてきたら:「作者(銘)」の有無や誰の作か、「時代」はいつ頃か、「素材」の質や希少性(特に良質な象牙や珍しい木材など)、「意匠の独創性」などが重要な評価ポイントになります。有名な根付師や蒔絵師の作品は高値で取引されます。
根付や印籠は骨董品の中でも特に人気が高く、残念ながら精巧な贋作や模倣品も存在します。信頼できる骨董品店やネットショップを選び、専門家の意見を聞きながら、納得のいくものを選ぶことが大切です。
まとめ:手のひらの小宇宙、江戸の美意識を愉しむ
根付・印籠・緒締は、実用的な道具でありながら、日本の職人たちの超絶技巧と豊かな想像力、そして遊び心が見事に融合した、まさに「手のひらの上の小宇宙」です。一つ一つに物語があり、江戸時代の人々の暮らしや文化、美意識が色濃く反映されています。
骨董品としての根付・印籠・緒締に触れることは、伊万里焼や掛軸などの骨董品とはまた違った、細密な手仕事の世界と、粋な江戸文化を体験する素晴らしい機会です。ぜひ、この小さな宝物の奥深い魅力に触れてみてください。あなたのコレクションに、あるいは日常のちょっとした楽しみに、新たな彩りを加えてくれることでしょう。